言葉の引き出しを増やす語彙力トレーニングの始めかた

「もっとうまく言いたいのに、言葉が見つからない」
誰もがこの瞬間を多く持っていると思います。このもどかしさ。頭のなかにはイメージが浮かんでいるのに、言葉にしようとすると、どこか物足りないし、「これじゃない」という感覚だけが残る。
これは語彙力の問題ではありません。
多くの方は語彙力を増やそうとして、新しい言葉を暗記することから始めますが、本当に必要なのは、知っている言葉の数ではなく、「使える言葉を頭から出す作業に慣れること」です。心に浮かぶイメージを、ぴたりとくる言葉で表現する。これは日々の小さな実践の積み重ねによって培われます。

語彙力トレーニングがうまくいかない理由
語彙力を増やしたくて、英単語を覚えるように、新しい言葉を暗記する方も時折見かけます。この方法で一時的に語彙は増えるかもしれません。しかし、実際の場面で適切に使えるようになることは稀です。
たとえば「憂悶(ゆうもん)」という言葉を知っているとします。意味は「深く悩み苦しむこと」です。
「この言葉の意味を理解しました。今から憂悶という言葉を使って、実際の会話や文章で使ってみましょう」
と言われても、その言葉を使うシーンがそもそも思い浮かびませんし、戸惑いを感じてしまいますよね。
新しく知った表現を自分の言葉にするには、単なる意味の理解では身についたとは言えません。言葉が持つニュアンス、使われる文脈、言葉の持つ重さや響き、くわえて、使うことで生まれる印象や雰囲気まで、総合的に理解していることが大切なのです。ですから、新しい表現を覚えるだけでは、語彙力が高まることにつながりにくいのです。
語彙力を上げるのは筋トレと同じ
筋トレを始めた方を想像してみてください。いきなり重いウェイトを持ち上げようとしてもできませんし、怪我につながるだけです。まずは軽い重量から始めて、少しずつ重さを増やしていく。重い重量を持てるようになるには、継続するしかありません。
語彙力も同じです。一度覚えた言葉も、使わなければ「ただ知っているだけ」です。逆に言えば、日々の小さな実践を積み重ねると、確実に力がつくと言えます。
目的は「心に浮かぶイメージを言葉にすること」
重要なのは「心に浮かぶイメージを、ぴたりとくる言葉で表現できるようになること」です。
心の中に浮かぶもやもやとした感覚や、微妙なニュアンスの違い。醸し出される雰囲気。それらを的確な言葉で表現できるようになれば、自分の考えや感情をより鮮やかに伝えることができます。
そのために必要なのは、日々の生活の中で言葉と向き合い、実際に使ってみる勇気と、それを続ける習慣です。

語彙力を上げるためにしたい3つの習慣
私たちの日常には、新しい言葉との出会いが散りばめられています。いいなと思う表現や言葉と出会ったら、自分の言葉として取り入れ、使いこなしていく。それが、語彙力を育てる最も自然な方法です。
机に座って単語を覚えることだけが、トレーニングではありません。毎日の暮らしのなかで、自然と取り入れる機会は多くあります。
1.心に響いた表現を記録する
「いいな」と思った表現に出会ったとき、記録します。可能なら、なぜその言葉が心に響いたのかも、簡単でいいのでメモします。きっとうまく書けません。でも、それでいいのです。
なんらかの「いいな」と感じるニュアンスがその表現にあったのなら、「今の自分に響く新しい表現」と出会えたわけです。その言葉が過去の自分の「言いたかったけれど、うまく言えなかったこと」を表現しているから、目に留まったわけですし。
ですので、それを記録する習慣をつけます。スマホでキャプチャを撮ってアルバムにしてもいいですし、メモアプリに書き写す、声に出して読んでみる。方法は何でもいいのです。大切なのは、その言葉との出会いを、その場限りで終わりにしないことです。
2.「マイ語彙辞典」をつくる
20代の頃、1のような表現に出会ったとき、メモ帳に表現をまとめていました(今もたまにやる)。ですが、記録数が多くなると、何の表現かわからず、使いたいと思ったときに探せません。そこで、ジャンルを分けてメモを管理するようになりました。
たとえば、私がつくっていたマイ辞典の種類はこんな感じでした。
- 心情を表す言葉
- 風景描写の表現
- キャッチコピーに使えるフレーズ集
- 企画書で使いたい表現
デジタルツールの利点は、検索できることにあります(とくにEvernote)。必要なときに、すぐに取り出せる形で言葉を貯めていくと、使いたいときにパッと取り出して使えるので、語彙が身につきやすいのも利点です。
それを開いて探して眺めているうちに、そこにある知らなかった表現は、自分の言葉として身につきます。
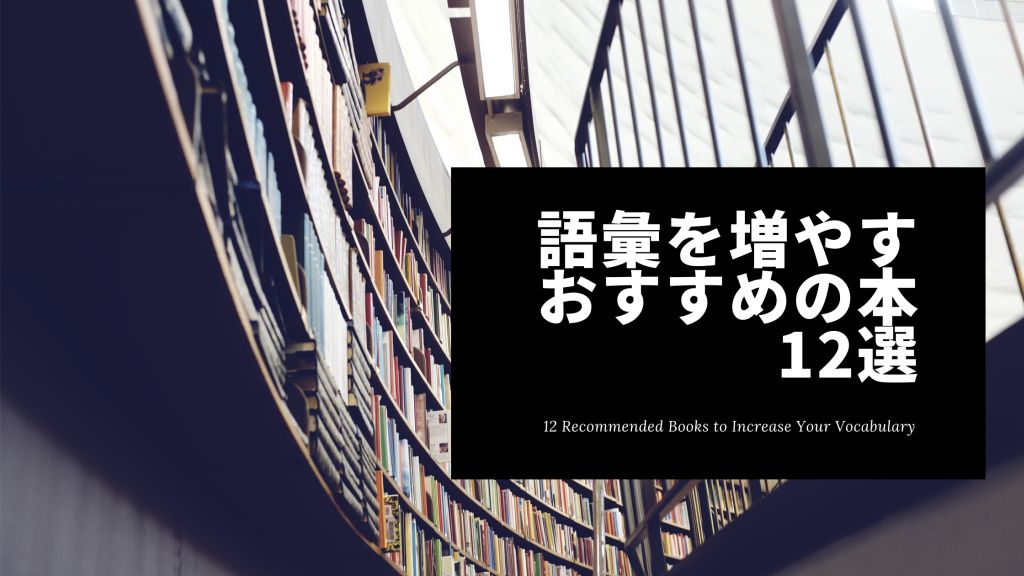
3.古い日本語を知る機会を増やす
いいなあと思うなめらかで味わいのある文章を書く方は、昔の文章(古文に出てくるような文学や随筆)や翻訳書を愛読していることが多いです。私もときどきそういう本を読みます。堅苦しくて古めかしい日本語を知ることで、今の言葉との差やリズムの違いがわかりますし、自分がどんな言葉をどんな気分で使いたいかがよくわかるからです。
令和の言葉は軽くてポップでわかりやすい。それも大事なことですし、ふつうに使いますが、心に浮かぶイメージを表すときは、古臭い日本語のほうが合うこともあります。そういう表現を知りたいし、自分の言葉にしたいと思っています。
米津玄師さんの歌詞にたくさんの人の心がつかまれるのは、日本語のニュアンスの豊かさ、鮮やかさに惹かれるのもあるのではないかと思います。「しぐるる」とか「鼻じろむ」とか「したり顔」とか。
大正・昭和の作家や歌人の作品は美しい日本語が多いので、興味があれば手に取ってみることをおすすめしています。すぐに読み慣れるものではありませんが、「一生かけて楽しむ趣味として少しずつ読めばいい」ぐらいで手に取ると、いつの間にか生涯の友になります。
たとえば、島崎藤村とか、石川啄木とか、正岡子規とか、坂口安吾とか、堀辰雄とか、二葉亭四迷とか、太宰治とか、宮沢賢治とか、永井荷風とか、遠藤周作とか。あと、何度も言ってますけど、山崎豊子とかね!
余談ですが、近現代文学の方々はwikiも併せ読むと人間臭さ全開(全壊?)ぶりを堪能できますし、おもしろいです。「この暮らしからこの表現が出てくるのか」と腹落ちもして、表現の味わい深さを感じられます。
長くなったので、続きは明日にします。
以下、続きです。








