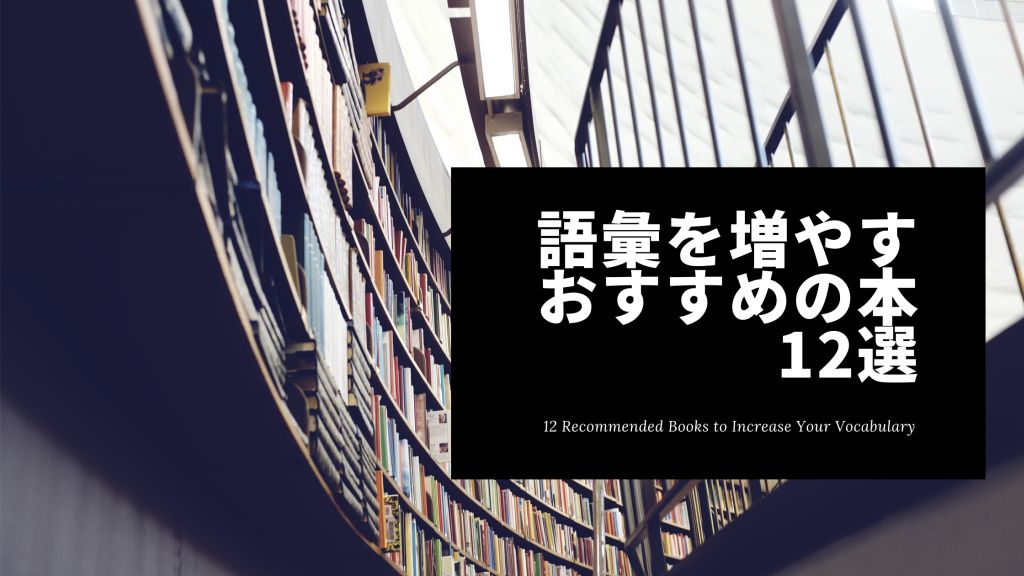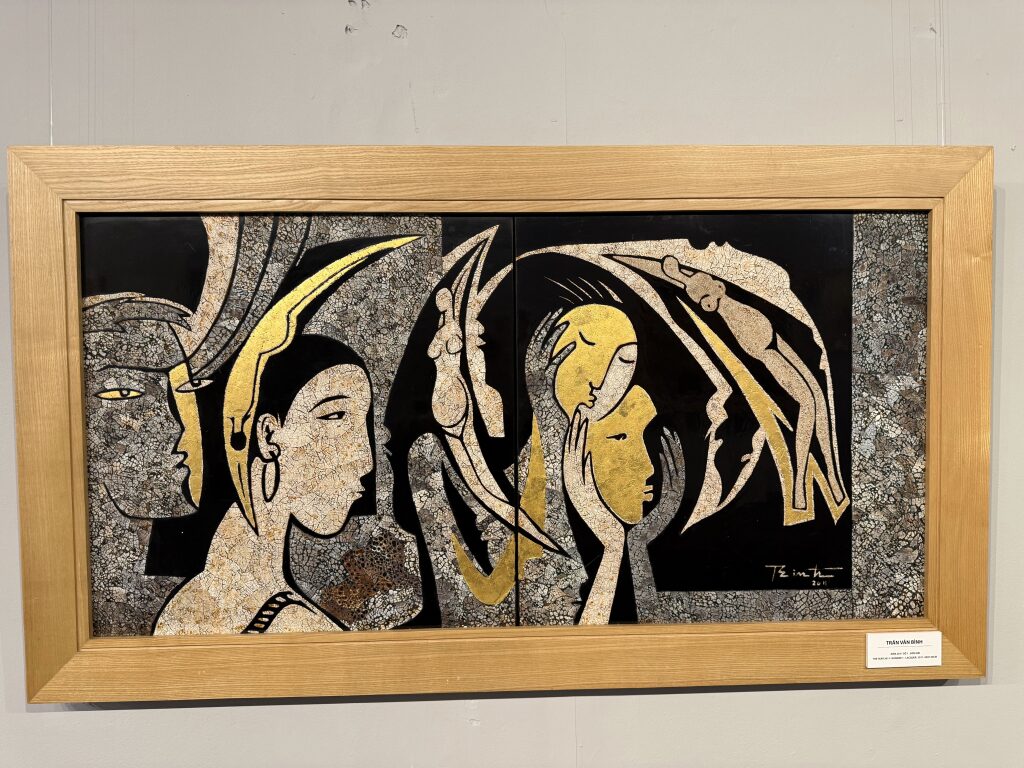自分の商品・サービスのよさを伝えるコンテンツの磨きかた

「商品の良さがうまく伝わらない」
「サービスの特徴をどう表現したらいいかわからない」
コンテンツ改善の相談でよく聞く言葉です。でも、それは「伝えるべき価値」に気づいていないだけで、既に存在しています。

伝わるコンテンツをつくる視点のもちかた
ブランディングを主力事業とする企業の改善事例を例に挙げてみます。その企業は、もともと経営者の方が上場企業でマーケティング・ブランディング・事業戦略を行っており、その道の超スペシャリストでした。
ですから、ご依頼いただいたクライアントに対して、ブランディングを行うために懇切丁寧にヒアリングや取材を行い、クライアント企業の強みを分析してビジュアルで理解できるようクリエイティブをつくっています。
そのクリエイティブは、クライアントの事業戦略も踏まえたブランディングとして提案されています。その企業にお仕事を依頼すると、キャッチコピーもできて、ビジュアルもできて、社内も社外も自社の価値がはっきりわかるようになる、みたいな感じで。それってなかなかできることではありません。「そこをお伝えしないのは、もったいない!」と、その点を自社の強みとして打ち出すようご提案しました。
たとえばですが、自社サービスの紹介文に、次の一文があったとします。
【Before】
「ブランディングのプロフェッショナルとして、お客様の課題解決をサポートします」
これを、経営者の方のスペシャリスト視点と出身を強みとして加えた一文にします。
【After】
「上場企業のマーケティング・ブランディング・事業戦略のスペシャリスト出身だからできる、御社の強みを活かした戦略的なブランディングをご提案します」
この変更で印象はずいぶん変わりますよね。ざっくりした例なので、この文章がいいかどうかは置いておいて(笑)。なぜ、この変更で印象が変わるかというと、
- 経営者が積み重ねてきた専門性を明確にした
- クリエイティブを手がける人物のスペシャル感を提供価値にを加えた
これらの点が可視化されたからです。
見えない価値を「見える化」する
商品やサービスが存在する際、価値は既に存在しています。ただ、関わる方にとってはその商品やサービスがもつ価値や存在理由は考えるまでもなく、あること自体があたりまえで、価値に気づきにくいもの。前述のブランディング企業の経営者の方は、
- マーケティングの専門知識
- 事業戦略の立案・実践経験
- ブランディングのスキル
- 高度なヒアリングを行える高いコミュニケーション能力
を能力や経験としてお持ちで、こういった背景をもっていることは事業を行うにあたってあたりまえのことだと考えていました。でも、このあたりまえこそが、その方ならではの強みなのです。
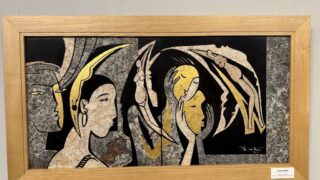
自分が持つ価値に気づけない理由
理由はおもに3つあります。
1.無意識の専門性
- 積み重ねてきた経験が「あたりまえ」になっている
- 日々の判断や行動が「暗黙知」になっている
- 自分特有のスキルだと気づいていない
2.価値の言語化の難しさ
- 「なんとなく」を言葉にできない
- 「みんなできること」だと思っている
- 自分の強みを過小評価している
3.日本人ならではの謙遜
- 謙遜したほうが角が立たたない
- 自分で自分のことを誇大化するみたいで恥ずかしい
とくに3番目が強い抵抗感を生みます。第三者である私から見て、「あきらかにこれはすばらしい点だよね」と思う点を言語化すると、「こんなことを自分で自分に対して書いたら恥ずかしい」「誰に何を言われるかわからないから言いたくない」とおっしゃる方もいます。でも、本当にそうでしょうか。
外部の目、第三者の目で見ると強みと言えるなら、そこは特徴として打ち出したほうがいいと私は思います。
余談ですが、雑誌の記事を書くとき、特徴が横並びの商品群をそれぞれの良さを引き立てながら、書き分けないといけない場合があります。そんなときは、どんな小さな違いも見逃さず、見せ方・表現の仕方ひとつで「スペシャル」な感じに書き分けます。比較商品の記事を読んで、「そんなに大差ないじゃん」と思うことってありませんか。そういうとき、商品レベルはだいたい同じです(笑)。
自社商品やサービスを打ち出すとき、いちばん最初にすることは比較ではありませんから、謙遜している場合ではないのです。何かスペシャルなことがあれば、それは書いたほうがいいのです。その商品やサービスを検討している誰かにとって、そのスペシャルが誰かのスペシャルになる可能性は十分にあります。

価値を見つけ出す具体的な方法
私がクライアントと一緒に価値を見つけていく際、必ず行うのが「なぜ」を深掘りすることです。
たとえば、
「なぜその事業を始めましたか」
「なぜその方法を選んだのですか」
「なぜその判断をしたのですか」
この問いかけを通じて、思わぬ発見があることも。
▼会話の例
「なぜブランディングの仕事をされているのですか?」
「以前の仕事で戦略設計と営業を担当していて、〇〇に注目して物事を判断するようにしています」
「その経験は今のお仕事にどう活かされていますか」
「そうですね、お客様の課題を分析する際に〇〇を見ると、なんとなく△△が見えるんですよね」
「具体的にはどんなふうに見えますか?」
「商品の強みだけでなく、事業全体を見て、〇〇が△△だと、◇◇になることが多いんですよね」
このように話を掘り下げていくと、その方の「あたりまえ」がどんなところにあって、ほかとの違いがわかってきます。話しているうちに、クライアント自身も、なぜ自分がこの仕事をしているのか、どうしてこだわっているのか、何がきっかけで今に至るのか、なぜこの仕事を今後も続けたいのかがわかってきます。そこに価値があります。

気づきが変える発信の質
おもしろいことに、自分がもっている無意識の価値に気づくと、発信するコンテンツの質が大きく変わります。その理由は、
- 自信と確信をもって言葉にできるようになる
- 具体的な説明を自分の経験を通して言葉にできるようになる
- お客様への提供価値が自分のなかではっきりする
こういった点にあります。
あるクライアントは「自分がなぜこの仕事をしているのか、改めて腹落ちしました」とおっしゃっていました。この「腹落ち」が、なにより説得力のあるコンテンツを生み出す源になるのです。
腹落ちすると、「こんなことを自分で自分に対して書いたら恥ずかしい」とか、「誰に何を言われるかわからないから言いたくない」という気持ちは、自然と小さくなります。むしろ、「確信をもってこの仕事をしているのに、なぜ言わないのか。自分が言わなくてほかに誰が言ってくれるんだ」と思ってくださることが多いです(笑)。
価値は既にそこにある
「商品やサービスの良さを伝えたい」
この思いは欠かせません。でも、大切なのは新しい価値を作ることではありません。既にそこにある価値に気づき、それを適切な言葉で表現することです。それこそが、伝わるコンテンツづくりの第一歩です。
自分のもつ価値に気づくには、次の3つを自分に問いかけてみてください。
- 「あたりまえ」を見直し、他人との違いを探す
- 今の商品やサービスを始めるに至った経緯を「なぜ」でさかのぼって考える
- 積み重ねてきた経験やスキルを言葉にしてみる
この過程を経ることで、より本質的な価値が見えてきますし、結果として説得力のある言葉を自分のなかに見つけることができます。その言葉は経験から発せられる生の言葉です。共感を得られやすい自分らしい言葉で、人に伝えることができるようになります。
それは同時に、自分の商品・サービスのよさを伝える言葉をいつも手元にもって、いつでもどこでも出せるようになる、ということなのです。