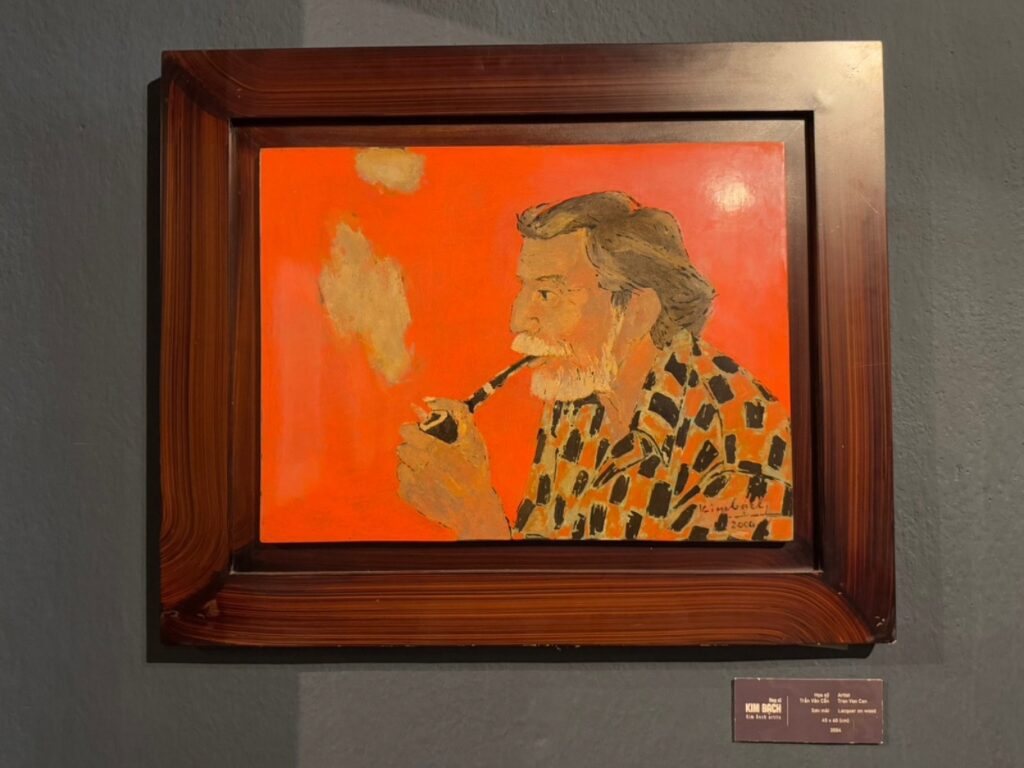語彙力を高めるための実践トレーニング

心に浮かぶイメージをぴたりとくる言葉で表現できるよう、語彙力を高めるトレーニングの始めかたの続きです。語彙力を上げるためにSNSなども使って、新しく覚えた表現を使う練習をします。実践を重ねることで、気持ちに合う言い回しを自在に使いこなせるようになります。

日常生活での実践トレーニング
言葉は使ってこそ、本当の意味で自分のものになります。ここでは、日常生活の中で無理なく取り入れられる、具体的な実践方法をご紹介します。
1.朝の5分間「言い換えチャレンジ」
朝、コーヒーを飲みながら窓の外の景色を眺めて、心に浮かんだイメージを言葉にします。もちろん、通勤時間でもOKです。たとえば、カーテンを開けて外を見たら、曇り空です。
「今日は曇りだな」
心に浮かんだ言葉が、このひとことだとします。これを別の表現で言い換えてみましょう。
「今日は空が重たげだ」
「雲が低く垂れこめている」
「灰色の空が街を包んでいる」
同じ光景でも、視点を変え、表現を変えることで、まったく異なる印象を伝えることができます。この小さな実践を、朝の5分間だけでも続けてみます。たった1行を3つに言い換えるだけですが、意外と難しくて、やりがいがあります。さらさらできるようになったときは、とってもうれしくなります。
2.書き写して、声に出して読んでみる
心に響いた言葉は、メモするだけでなく、実際に書き写してみます。手で書くと、心に残りやすいです。また、あるときは声に出して読んでみます。これは、言葉のリズムやテンポ、響きを体で覚える練習になります。
とくに古い日本語や美しい表現に出会ったときは、声に出して読むことで、その言葉の持つ独特の韻律や味わいを、より深く身体で理解できます。
たとえば、『平家物語』の「扇の的」。この文章は高校の古文で習いましたが、日本語の美しさと発音したときの美しさが好きで、音読して覚えた文章。ときどき思い出して、ネットで探して音読してます。
以下は、原文を声に出して読む用に読みやすく書き換えたものです(間違ってたらごめんなさい)。
与一、かぶらを取ってつがい、よっぴいてひやうど放つ。小兵というじょう、十二束三伏、弓は強し、浦響くほど長鳴りして、あやまたず扇のかなめぎは、一寸ばかりおいて、ひいふっとぞ射切ったる。 かぶらは海へ入りければ、扇は空へぞ上がりける。春風にひともみふたもみもまれて、海へさっとぞ散ったりける。

3.誰かに読んでもらうための「5行エッセイ」を書く
日記は自分のために書きますが、エッセイは誰かに読んでもらうために書く散文です。この「誰かに読んでもらう」という意識が、より洗練された表現を探す無意識のモチベーションになります。
「5行」という短さには理由があります。短いと逆に難しくなりますし、長すぎず、短すぎず、続けるにはちょうどいい長さなのです。5行あれば自分のなかに浮かんだイメージを、ある程度まとまった形で表現することができます。
たとえば、先ほどの朝の風景を5行のエッセイにしてみます。
低く垂れ込めた雲が、街を優しく包みこんでいる
湯気の立つコーヒーカップを両手で包む
窓ガラスに小さな雫が伝い始めた
もうすぐ雨が降るのかもしれない
それでもどこか穏やかな、幸せな朝
こんなふうに心に浮かんだイメージを、誰かに伝えるための言葉に変換していく。この作業を繰り返すことで、自然と表現力は磨かれていきます。
上記はなんだか詩のようですが、思い浮かぶことをつらつら書き連ねてもOKです。たとえば、こんなふうに。
今朝は曇り空で、雲が低めに出ています。いつもどおり、コーヒーを入れてカーテンを開け、窓際に立ちます。湯気が立つカップを両手に持ち、温かさを感じながら外を眺めています。窓に水滴がつき始めたのを見ると、これは雨が降りそうです。天気は思わしくありませんが、不思議と心が落ち着く、そんな朝の時間です。
なんでもいいのです。とにかく書く。短くても長くてもいい、とにかく毎日続けます。そして、気長にやること。それが重要です。
余談ですが、私が新卒で編集の仕事を始めたときは支離滅裂な文章しか書けませんでした。ですが、こういったトレーニングを続けて、3年後にはライターさんの代筆もできるぐらいの筆力になり、5年後には、先輩からちょっと手直しが入る程度の原稿が書けるようになりました。それからずっと売るための文章を書き続けています。
とにかく気長にコツコツやるのがポイントです。
SNSを活用した小さな発信の習慣
頭に浮かぶイメージを言葉に出して使うことは、慣れが必要です。 今は人に読んでもらえる場所がたくさんありますので、ブログ・X(旧Twitter)・Instagramなどに投稿するのもおすすめです。
誰かに反応してもらえるかもしれませんし、誰にも反応されないかもしれません。反応されなくても気にせず、とにかく続けることです。書き続けるうちに言葉があふれ出すようになります。
おすすめは、Instagramへの写真+散文の投稿です。実名だとやや気恥ずかしいので、アカウントネームで。ポエムアカウントのようになると思いますが(笑)、そこは気にせずにやります。
たとえば、夕日の写真と5行エッセイを投稿する場合。

ビルの隙間から差し込む夕陽が
アスファルトを黄金色に染めていく
都会の夕暮れは、いつも突然やってくる
「#キリトリセカイ」のハッシュタグなどを使って投稿すると、同じ言葉の雰囲気や写真を好む方にレコメンドされるようになります。X(旧Twitter)でこういう内容を投稿すると、「どうしました?」とざわめきが起こるかもしれませんが、Instagramなら同じ気持ちでイメージや言葉を紡ぎたいお仲間さんが見つかります(笑)。
このように日常の一コマを切り取り、自分の言葉で表現してみます。写真と言葉を組み合わせることで、視覚的なイメージと言葉の関係性も意識することができます。画像を見て、頭のなかから表現を引っ張り出す練習にもなります。

反応の有無にとらわれないのがポイント
SNSでの発信で注意したいのは、「反応」を気にしすぎないことです。「いいね」の数や返信の有無は、表現の質とは必ずしも比例しません。大切なのは、自分の心に浮かんだイメージを、自分の言葉で表現する練習を続けることです。
むしろ「誰も反応しない」と思うことで、より自由に、より正直に、自分の言葉で表現することができます。これは、語彙力を育てる上で、とても大切な心の在り方です。言葉の受け取り方は人それぞれ。狙ったものが狙ったように反応されることのほうが、実際は少ないです。
心に浮かぶイメージを3つの視点で表現する
最後にもうひとつ。今、目の前にある光景を、3つの異なる視点で表現してみる練習です。次の3つの視点を使います。
- 物理的に描写する
- 感覚的に描写する
- 感情的に描写する
たとえば、デスクの上の白いコーヒーカップを見て感じたことを、3つの視点を使って1行で書いてみます。
【物理的な描写】
白い磁器のカップに、黒い液体が七分目まで注がれている
【感覚的な描写】
ふわりと立ち昇る芳醇な香りが、午後の仕事場を満たしていく
【感情を込めた描写】
まだ温かい珈琲が、疲れた心を優しく癒してくれる
こんなふうに、同じコーヒーカップも、視点を変えるとまったく異なる視点で表現できます。この演習を日常的に行うことで、状況に応じた適切な表現を選択する力が自然と身につきます。
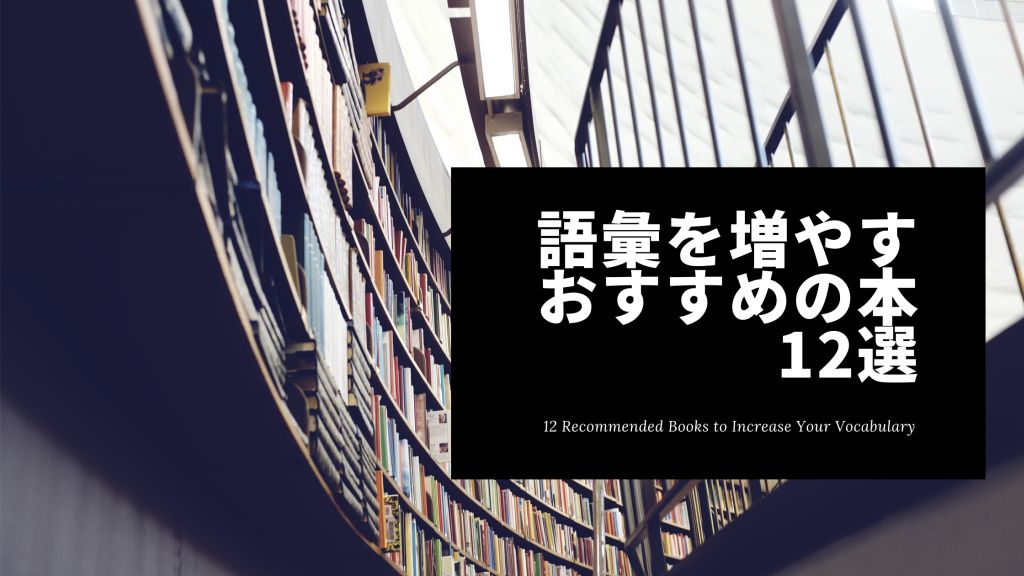
言葉の引き出しを増やし続けるために
語彙力を育てることは、難しい言葉を使えるようになることではありません。自分の心に浮かぶイメージや感情を、より正確に、より豊かに、自分の心にぴたりと合う言葉で表現できるようになることです。これらの習慣をぜひ続けてみてください。
- 心に響く言葉と出会ったら、記録する
- 記録した言葉を、日常で使ってみる
- 誰かに読んでもらうことを意識して、5行エッセイを書いてみる
こうした日々の小さな実践によって、語彙力は誰にでも身につけられます。気長に続けることで、少しずつ、でも確実に、誰かの心に届く言葉を書きこなせるようになります。