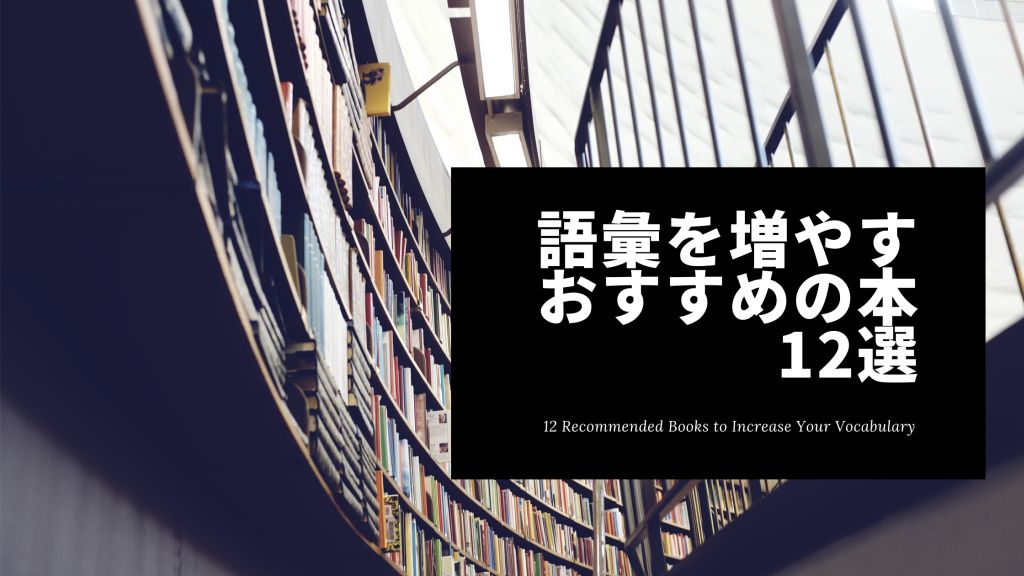編集視点で考える、ブランドストーリーのつくりかた

「ブランドストーリーを作りたい」というご相談もよくいただきます。「でも、うちには特徴的な何かはないし、価値と言えることも普通のことしかないんです。それでも何かをストーリーにすることってできますか?」と尋ねられます。
大丈夫です。どんな場合もストーリーの種はあります(早い安いうまいとか、大量生産などといった場合は難しいです)。
なぜストーリーが心を動かすのか
20年以上前、私が編集者として手がけた一冊の本の話です。どの会社にもパソコンはまだ各部署に1~2台しかなく、口コミサイトもない時代に、在宅介護をされている方々の経験をまとめる本をつくりました。
ごく個人的なノウハウをひとり1点ずつ紹介するものでしたが、その本は何度も重版がかかりました。当時そういった個人のノウハウを紹介し、一覧化されている本が少なかったのも理由だと思います。
この本が売れ続けたのは、「誰かの実体験」には人の心を動かす力があったからです。カタログのようなきれいにまとめられた情報ではありませんでしたが、実際の経験に基づく言葉には、説得力があります。今、何かモノを買うとき、口コミをやレビューを参考にするのも同じ理由ですよね。
価値を見つけ出す対話から始める
「なぜ」を探る
ブランドストーリーを作る際、私がまずお伺いするのは次の3点です。
「このサービスや商品を作ろうと思った最初のきっかけはなんですか?」
「なぜそれが良いと思ったのですか?」
「そのサービスや商品を通じて、顧客にどんな体験をしてもらいたいですか?」
シンプルな質問ですし、よく聞かれることだと思いますが、この問いかけをきっかけに深掘りしていくと、思いがけない物語が見えてくることがあります。
この質問に答えられない場合は、ストーリーは見つかりません。
ある介護事業所の課題
「採用の質を上げたいので、自社サイトに掲載するコンテンツを工夫したい」とある介護事業所からご相談を受けました。
介護業界では「アットホームな職場」を強調する企業が多いのですが、その企業はアットホームではあるけど、メリハリのある会社組織をつくりたいという意図をもって運営されていました。採用コンテンツには、その点をうまく伝え、「会社組織のメンバーとしてひとり一人に働いてほしい。馴れ合いではなく、組織人として行動できて、かつ社風に合う人物を採用したい」というご希望がありました。
「その人らしさ」を言語化する
個人の「思い」を形にする
「アットホームだけど、メリハリのある組織」
この言葉は表面的には矛盾するように見えます。でも、ここにこそ、企業らしさが隠れていました。そこを言語化するために、
- 社長へのヒアリング
- 役員の方々へのアンケート
- 現場スタッフの声の収集
を行いました。それを受けて、会社の特色やどんな人物が「ウチの社員ぽい感じか」を言葉にしていただきました。それをもとに、社長や役員のみなさんで「ウチの社員はこんな感じであってほしい」と思う共通認識を言葉ですり合わせて。出てきた価値観はこんな内容です。
「利用者様に寄り添うためには、職員同士の馴れ合いとは区別する」
「プロとしての自覚を持って働く環境づくりが大切」
「だからこそ、組織としてのありかたを重視している」
この価値観は、普段言葉で語られていなかった「暗黙知」でした。言葉になったことで、会社全体の共通認識になりました。ですから、これらをもとにコンテンツイメージを企画・立案し、それに基づいた撮影や記事作成を行いました。
結果、採用活動においても、その認識をもとに活動できるようになり、入社後のミスマッチが減り、社員の定着率は上がりました。
言語化がもたらす変化
価値観が言葉になると、多くの場合、次のようなことが起こります。
- 採用時のミスマッチが減る
- 社員の定着率が上がる
- 組織の一体感が強まる
なぜなら、「ウチの会社ってこういう会社だよね」という共通認識が、経営者をはじめ現場スタッフまで、しっかり共有されるからです。雰囲気にも出るようになりますしね。
ストーリーを形にする実践的な方法
構成のポイント
私がとくに意識しているのは、「結起承転結」の構成です。読み手にとって苦痛なのは、自分が何を読まされているのかわからない文章です。
- 最初に結論がわかる
- 論理的に内容が展開される
- 最後にまとめがある
ストーリーに大切なのはこの3点。普段からとても気を配っています。
ストーリーの具体的な組み立て方
組み立て方としてはシンプルで、情報を集めて、軸となる価値観を決めて、それを季節やタイミングと掛け合わせることです。最初の情報収集でどれだけ集められるかが、ストーリの濃さ・深さを決めるカギになります。
1.価値観をみんながわかる言葉にする
- 価値観のもととなる情報を集める(最重要)
- 軸となる価値観を定める
- 様々な切り口で表現する
- 季節やタイミングと掛け合わせる
続いて、そのストーリーがこれからも続いていくことを示す場合は、発信の仕組みをつくります。更新日を決め、公開する情報の基本構成(フォーマット)を決めます。たとえば、ブログ記事は画像1点+テキスト2000文字とか、SNSは画像3点+テキスト文にするとか。投稿するフォーマットが決まっていれば、毎回中身を考えるだけで済みます。
2.発信の仕組みをつくる
- 更新日と更新頻度を決める
- 公開する情報の基本構成を決める
ストーリーは既にある
ブランドストーリー作りで大切なのは、新しい物語を作ることではありません。
すでにそこにある物語を見つけ出し、実体験をもとにした言葉にすることです。それが本質的なブランドストーリー作りの第一歩です。ストーリーを見つけるのは難しくありません。次の3点で誰にでもできます。
- 「なぜ」を丁寧に探る
- 無意識の価値観を言葉にする
- 論理的な構成で伝える
これが明らかになることで、自分や会社の存在意義を実感できますし、継続的な情報発信の大きな原動力となります。心の目覚め・気づきから行動に至る過程を示し、その結果生まれたもの。それがストーリーの本質なのです。